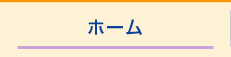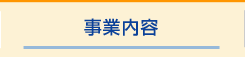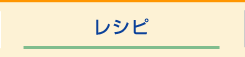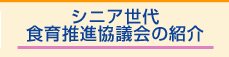平成24年度事業内容
シニア食育講座
シニア世代の食生活の改善に係わる人々を対象に、望ましい食生活のあり方を学習する「シニア食育講座」を東京都、群馬県、新潟県で開催しました。
1.講座の概要
| 日時 | 平成25年2月11日(月・祝)13時半~17時 | |
| 内容 | 「健康寿命を延ばすための食事」 講師:本多 京子(医学博士・管理栄養士) 「『早寝早起き朝ご飯』のサイエンス」 講師:柴田 重信(早稲田大学先進理工学部教授) |
|
| 会場 | 高崎市市民活動センター ソシアス(活動室) | |
| 参加者 | 地域の高齢者支援活動に関わっている方、関心のある方 | |
| 主催 | 特定非営利活動法人じゃんけんぽん シニア世代食育推進協議会 |
|

本多京子先生の講義風景

柴田重信先生の講義風景
2.講義内容の概要
「健康寿命を延ばすための食事」
講師:本多 京子(医学博士・管理栄養士)
- 健康寿命が大切
日本の平均寿命は男性79歳、女性86歳だが、健康寿命との差(2010年)が男性で約9年、女性で約12年である。健康寿命を延ばすためには、血管年齢、骨年齢、腸年齢、脳年齢が重要な機能を担う。 - 血管年齢(血管年齢の若さを保つには、メタボ予防が大切)
特定健診・保健指導の実施基準として、お腹周り、血糖値、血中脂質、血圧があげられる。
<食べ方のコツ>
①まずは、実だくさんの温かい汁ものや野菜料理から食べ始めましょう。
②肉や魚の主菜は1品にして、副菜2品をそろえましょう。
③朝食はしっかり、遅い夕食は軽めにしましょう。
④揚げ物や炒め物は続けてとらないようにしましょう。 - 骨年齢(骨は生まれ変わっていきます!骨の若さを保ちましょう!)
破骨細胞の働きを抑え、骨芽細胞の働きを助けるビタミン・ミネラルを摂取するよう心掛けましょう。
<食べ方のコツ>
①牛乳とヨーグルトを合わせて、毎日300mlとりましょう。
②魚の缶詰や小魚(酢を合わせて)をとりましょう。
③大豆製品(豆腐や納豆)を毎日、とりましょう。
④青菜やごま、海草も忘れずにとりましょう。 - 腸年齢(お腹すっきり、腸年齢の若さを保ちましょう!)
食物繊維やオリゴ糖の摂取で腸内細菌のバランスを良くしましょう。
<食べ方のコツ>
①根菜や豆類(食物繊維・オリゴ糖)をとりましょう。
②ヨーグルトや納豆など発酵食品をとりましょう。
③ひじきや乾物、きのこで常備菜を作りましょう。
④おやつには、芋、果物、ドライフルーツ、干しイモ、甘栗などをとりましょう。 - 脳年齢(脳の若さを保ちましょう!)
青魚や青菜の摂取とともに、バランスのとれた規則正しい食事をとる、自分で調理するなど食習慣にも注意しましょう。
<食べ方のコツ>
①食事代わりにおやつをとるのは止めましょう。
②煮物にご飯だけではダメ。年をとっても、肉や魚・大豆タンパク質は減らせません。
③しっかり噛んで食べましょう。
④塩分・油脂のとりすぎを防ぐために、市販の惣菜に頼りすぎないで賢く利用しましょう。
⑤自分で料理すれば、段取り力アップで脳が活性化します。
「『早寝早起き朝ごはん』のサイエンス」
講師:柴田 重信(早稲田大学先進理工学部教授)
- 体内時計とはなにか
哺乳類においては、90分周期(睡眠・覚醒)、約24時間周期(一般的)、その他1月周期、1年周期などのリズムで生体の働きと時間情報が深く関わっている。このなかで、24時間周期については、時計遺伝子が発見され分子基盤がわかっている。 - 体内時計と光リセット
種々の疾病の症状には日周リズムのあるものがわかっており、例えば喘息の症状は朝早くに悪化しやすく、心筋梗塞や脳梗塞は早朝から午前中に起こりやすい、また、自動車事故は真夜中に多発するなど、日周リズムは、いろいろな分野で重要性を持っている。
体内時計に支配されている睡眠時刻は、毎日少しずつ遅れていくが、起床時に光の照射がある(朝日を浴びる)と24時間にリセットされ、眠る時間が早まり遅れなくて済むが、寝入りばなに光があると体内時計が遅れ、ますます朝起きが辛くなる。すなわち、「夜更かしは得意だが早起きは苦手」が一般的だが、これは体内時計の周期が24時間より長いからであり、体内時計の乱れは、健康に悪影響を与える。 - 体内時計と食・栄養の関係
食物や栄養などの吸収や働きを考えると、摂取時刻によって栄養の働きが異なる可能性がある。これらをサイエンスとして考えると、食事は、栄養素の構成や摂取量のみならず「いつ食べるか」という摂取時間も重要な要素である。体内時計は、食・栄養素の消化、吸収、代謝、排泄のいずれの過程にも影響を及ぼし、同じ食べ物でも夜間に食べると太りやすいと言われている。このことを解明するのが、「時間栄養学」である。
一方、体内時計の乱れは、健康に悪影響を及ぼすので、リセットする必要があるが、朝日と同様に食事が体内時計に働きかけることで体内時計をリセットすることができることがわかってきた。このことを解明するのを「体内時計作用栄養学」とよぶ。 - 体内時計作用栄養学
体内時計は、光の刺激又は食事の刺激でリセットされる。
①体内時計は、長い時間絶食後の食餌の時刻に依存する(朝食のほうが夕食より効果が高い)。ただし、食事量が多いと強力にリセットされる。
②1日4食以上の食餌で均等に食べていると体内時計のリセットが生じない(ダラダラ食いは体内時計をリセットしない)。
③1日3食で、夜遅くに1食食べるよりも、魔の時間(夜中)を避けて通常の夕食と夜中に分食すると体内時計が乱れにくくなる。 - 時間栄養学(食べ方と肥満)
1日1食より2食、さらに朝食にウェイトを置いた食餌のほうが太りにくいという実験結果がある。
食習慣が乱れて、夕食比率が高くなると脂質代謝関連遺伝子の発現で内臓脂肪や体重が増加しやすくなる。これに対して、朝食をしっかり摂るバランスの取れた食生活が、肝臓の時計リセットとダイエットに有効である。
すなわち、乱れた食習慣を改善することが肥満やメタボリックシンドロームの予防につながる。